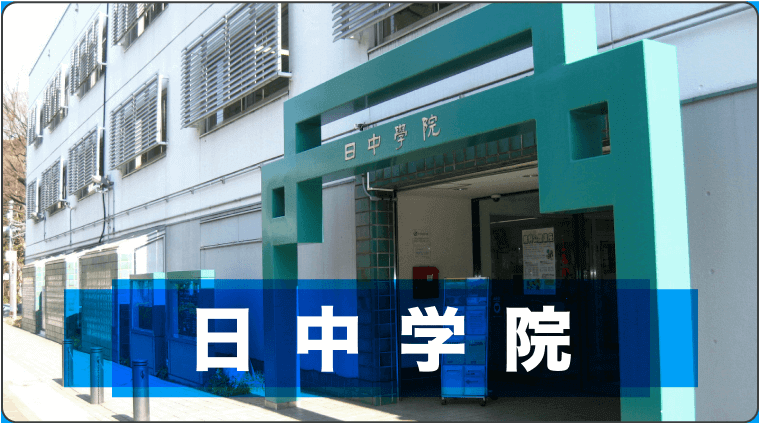今どき北京はこう歩く・2025年度版
第2回
第2回
「中国産?絶対ダメよ!!」・・・、
それちょっと違うかも。
熱い話題は“未来都市”
私には “北京の弟” がいる。知り合ってすでに30年以上、家族ぐるみの付き合いで、亡き母もまるで「ウチの子」のごとく、とても可愛がっていた。
彼、Kくん(すでに中年)は、 私が北京に行く折は、 仕事の都合がつく限り、 必ず空港まで迎えに来てくれる。 毎回 楽しみにしているのが、空港から市内のホテルに着くまでの間、彼が何を話すかである。開口一番彼が口にする話題は、その時 Kくんが最も関心を持っていること、つまり「中国・北京で最も熱いテーマ」に他ならない。
では2025年初夏、 Kくんの頭を占めていて、 日本から来た 「お姉ちゃん」 に知らせたい話題は何だったのか。「EV・電気自動車」と「自動運転車」である。
北京首都空港から北京市内へと向かう道路―。
「車のナンバープレート見てごらん。緑色のものが電気自動車だよ」
緑色のナンバー?走っている車の半分は緑じゃないか!? 中国では半分が電気自動車ってことなの?
「そういうこと」
ここまで多いとは知らなかった。いったい何故だ?
「何故って、節約になるからさ。 充電一回で50元(約1,000円)だからね」

緑色のナンバーは電気自動車
電気自動車の場合、一回の充電で普通の一般家庭であれば、一週間はもつのだそうだ。ちなみに普通のオイルだと満タンで300元(約6,000円)はかかるという。電気代が高い日本では、 酷暑のなか恐怖におののきながらエアコンを使っていた私には、 電気代が安いという概念は実感が伴わない。
そしてもうひとつ、Kくんが熱く語ったのは「自動運転車」についてである。
「今試乗キャンペーンをやっているんだ。予約殺到で、なかなか取れないんだけど、滞在中に予約取れたら乗りに行こう」
昭和の私、免許はマニュアルで取得している私にはついていけない話題である。
Kくんが教えてくれた自動運転車の紹介動画を見ると、まさに未来都市、鉄腕アトムの世界だった。
駐車場で人差し指を曲げて 「おいで、おいで」 という動作をすると、ピカリと光り、停車中の車が通電を始める。そして忠犬のごとくご主人様のところまで移動してくるのである。走り出してからは、ハンドルに手を添えるだけであとは“お任せ”だ。
圧巻は駐車場に車を停める時である。車社会の中国では、巨大な駐車場であっても、空きを見つけるのは大変な作業だ。渋滞とともに、車社会の大きな屈託となっている。
ここでも自動運転車は力を発揮する。適当な場所で車を降りれば、あとは車本人が場所を探して、停車してくれるのだそうだ。
ファーウェイ系列の自動運転車、その広告キャッチコピーは以下の通り。
“想界样 就界样”(思いのままに)
「自動」にも距離がある
Kくんの他に、北京では会いたい人たちは多くいるが、「北京稲門会」の仲間もほぼ30年来の友人たちだ。あの頃日本留学から戻ってきたばかりの若鷹たちは、今では21世紀を牽引する中国社会で大きく羽ばたいている。
彼らとの食事会も大変楽しいもので、そこで話題になるのはやはりその時々に注目を集めている話題に他ならない。
今年の話題は何だろう?
Kくんと同じだった。自動運転車の試乗会情報で盛り上がり、まぎれもなく、今北京の熱い話題は“近未来世界”だった。
章弘さんは北京稲門会の重鎮の一人である。彼は 元CCTVのプロデューサーで、CCTVの日本関係報道の第一人者として長く活躍していた。 物事を見る目、感性は一流で、彼に一時間話を聞くと、本を書く時の一章分が出来てしまうから不思議である。感謝他!
そんな章弘さん、2025年5月末時点での興味は、やはり「自動」である。
自動運転車は言うまでもない。が、彼が改めて感心したのは「日本」製の「自動」だった。
つまりはこういうことである。
「先日、 あるレストランでトイレに行ったんですよ。 個室のトイレ、 一仕事終えて水を流そうとしたらフラッシュがない。自動流水だなとわかって、少し離れたんですが、何故か流れない。便器の右や左と身体を動かしても、流れない。 焦りました。 外では 順番待っている人がいるし、 どうするか・・・、人を呼ぶか・・・、とドアに向かった途端、ようやく水が流れたんですよ」
章弘さんの感覚では 「日本製の自動流水は20∼30センチほど離れれば水は流れる。しかるに中国製は1mくらい離れないと流れない」 のだそうだ。
章弘さん、 お待たせしました、 と言いながら次のひとに個室を明け渡し、 自身は手を洗っていると、次に個室に入った人が扉を開けて、申し訳なさそうに言った。
「失礼ながら、このトイレどうやって水を流せばいいのでしょうか、教えてくれませんか」
・・・。
日本製と中国製は、似て非なるものも多いが、 章弘さんの自動流水体験で思い出されたのが、10年前、中国にもシャワートイレが出回り始めた頃のことである。
中国で中国製のシャワートイレを使った某駐在員の体験談。
「温水ボタンを押したら、いきなり熱湯が出たんです。びっくりして便座から離れたんですが、止まらない。まるで噴水のように熱湯がトイレ中に溢れて、床も水浸しになりました。吹き上がる熱湯をかいくぐって、ストップボタンを押し、ようやく止めることができたんです。翌日修理の人を呼んだのですが、お湯の温度は下がらないまま、結局日本製のものに変えてもらったんですよね」
こういうことを言うと、まるで中国の「自動」が “まだまだだねー” 、というような誤解を受けるが、自動運転車をはじめ、今では日本が後塵を拝しているものも多い。

かつての“八佰伴”、建国門の賽特
私の最新体験。
建国門の賽特百貨店といえば、創業当初は「八佰伴」として知られ、北京在住日本人のオアシスだった。30年経った今は、百貨店が閉業し、レストラン街と化している。
今回、 そのうちの一軒に連れて行っていただいて、 美味しい料理を堪能したが、帰る間際トイレに行った。豪華トイレで、 もちろんシャワートイレ、 自動流水である。しかし、いくらさがしてもトイレットペーパーが見当たらない。 ペーパーホルダーはあるのに ペーパーが切れているようだ。予備のロールもない。詰まっているのかも、と思い手を近づけてみると、びっくり!自動でペーパーが出てきたのである。
日本ではまだまだ見ることができない領域の「自動」だった。
絶対欲しい「中国産」は?
中国産といえば、びっくりしたことがある。帰国して間もない頃、近所の八百屋さんでのことだった。上品そうなおばあちゃまが野菜を買っていらしたのだが、その時 店員さんにこう確かめていた。
「これ日本産よね?中国じゃないわね?中国産はダメよ、絶対ダメ!」
それを聞いて、 私の脳裏に浮かんだのは、 北京の市場である。スーパーではない、 農貿市場と呼ばれる自由市場だ。 その八百屋さんの数十倍ほどの敷地に、 所狭しと並んだ野菜や果物、 見たこともないような種類のものもあって、 しかも安い。 中国産はダメ、 とおっしゃったおばあちゃまは、 多分農薬のことが頭にあったのだろうが、 現代中国では、 食の安全問題は相当意識が高いので、 私は気にしたことがない。
自由市場は衛生的にどうか・・・、と躊躇される方は、スーパーに行ってください。

農貿市場(自由市場) 日本では見られない果物や野菜が豊富
撮影:青樹明子
6月初めの北京で、Kくんに「スーパー行こう」と誘われて行ったのが、EC大手、「京東」が直接経営するスーパーである。
これもまたすごい。
広い敷地、 豊富な品物、 プライベートブランドも含め、 価格が安い。しかもすべてが清潔だ。お米売り場では、 最近日本のスーパーでは見ることができないほどの量のお米が売られている。5キロでだいたい1,500円ほどで、買って帰りたいという気持ちを抑えるのに苦労した。

スーパーのお米売り場
中国の友人は笑う。
「中国人はみんな日本に行って買い物したがるのに、中国で必死に買い物する日本人もいるんだね。何故だい?」
何故だろう。
品物によっては、日本産を超えられないものがあるからだ。
私が、中国で必ず買うものはというと・・・、
同仁堂にて 風邪薬(冬用&夏用) のど飴 傷薬 口内炎治療薬
稲香村にて 北京伝統のお菓子(月餅の時期には、トランク一杯買い込んだことも)
天福茗茶にて お茶で作ったお菓子(なかでもかぼちゃの種とお茶のミルフィーユは亡き山口淑子先生が気に入ってくださったので、毎回お送りしていた) 菊花茶・・・
地元スーパーにて キクラゲ 調味料 スナック菓子 果物茶
トランク満タンになるほど、買わなきゃならないので、短期間でも特大トランクで行かなきゃならない。

稲香村のお菓子、北京伝統の味。月餅はコロナ前までトランク一杯買ってました
撮影:青樹明子
最後に番外編で、章弘さんの買い物話をひとつ。私はこの話が大好きなので、お付き合いいただければ幸いです。
章弘さんがいまだに忘れられない買い物は、2009年の冬だったそうだ。場所は新宿、小田急百貨店だったという。
「タカキューのバーゲンでした。そこで僕は94%カシミアというロングコートを見つけたんです。デザインも新しく、実にかっこよかった。それがいくらだと思います? 1万円ですよ、1万円!北京に戻って同僚たちに自慢すると、大騒動になりました」
中国でカシミアのコートを買おうとすると、当時でも日本円で8万円は簡単に超す。しかも、デザイン、質には疑問が残る。
同僚たちは、そのカシミアコートを見て、全員が「自分も欲しい」と言い出した。
さて、どうしたもんか。みんなで話し合った結果、買い物係を選出しようということになった。飛行機代をみんなで負担して、買い物係を日本に送り込む。そして章弘さんと同じカシミアのコートを一人1枚分、買ってきてもらうという計画である。明日にでも行かないと、バーゲンは終わってしまう・・・、同僚たちが真剣にコストの算出をしている時、章弘さんは突然思いついた。
「待てよ、そういえば今ちょうど、○○が日本にいる。あいつに頼もう」
ということで、依頼を受けた○○さんは、即刻新宿に向かい、タカキューでコートを十枚買って、中国に持って帰ったのだそうだ。
○○さん、重い荷物をご苦労様でした。

スイーツに綿菓子が多いのは何故?
提供:青樹明子
今回、北京でゲットした私の収穫物、そろそろなくなるので、早く次の買い物にいかなくては。
(続く)

青樹 明子
愛知県生まれ。ノンフィクション作家。
早稲田大学第一文学部卒、同大学院アジア太平洋研究科修了。
1995年より2年間北京師範大学、北京語言文化大学へ留学し、98年より北京や広州のラジオ局にて、日本語番組の制作プロデューサーやMCを務める。2014年に帰国。著書に『中国人の頭の中』『中国人が上司になる日』『日中ビジネス摩擦』『「小皇帝」世代の中国』『家計簿からみる中国 今ほんとうの姿』等。