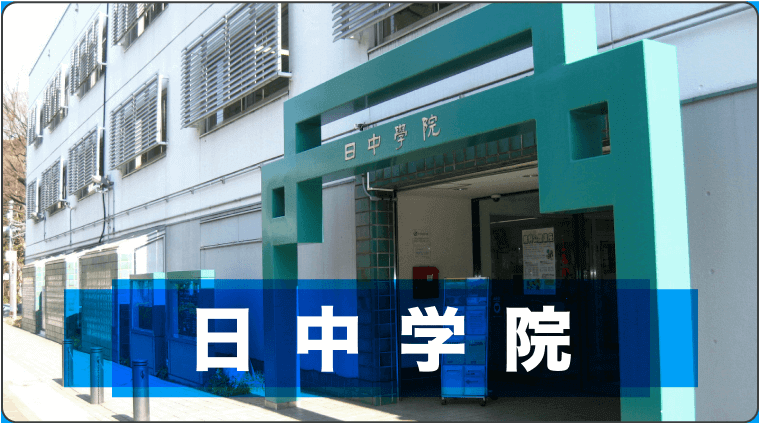「JENESYS2025」日本大学生訪中団第1陣
本事業は、中国日本友好協会の招聘に応じて大学生・大学院生を中国に派遣し、「中国とのふれあい」をテーマに、大学訪問やテーマに関する視察・交流等を通じて同世代交流を行うことで、両国の若者の間に友情を醸成し、相互理解の更なる深化を目指す。また、5月29日(木)に北京で開催する中日青友好交流大会に参加し、日中両国の友好関係の更なる促進を目的として実施しました。








Contents
Highlight
中国の2大学を訪問して同世代と交流
南昌大学では、中国人学生と一緒に昼食を食べ、日本学生が「日本人の見えない精神」について発表したほか、端午節に合わせ香り袋作り体験をする等して交流しました。北京師範大学では、中国大学生の案内によるキャンパス見学や、文化体験として漆扇作り・書道体験を行いました。各大学で日中の学生同士、互いの専攻や興味、将来についてなど話しあい、親睦を深めました。連絡先を交換してその後も交流を続ける様子も見られました。
中日青年友好交流大会に参加
大会には、金杉憲治 駐中国日本国大使、楊万明 中国人民対外友好協会会長、鄭新業 中国人民大学副学長のほか、日中両国の大学生など約600人が参加しました。
本団の団員は、学生代表のスピーチのほか、合唱とダンスを披露し会場を盛り上げました。
実施概要
| 派遣期間 | 2025年5月24日(土)~5月30日(金) 6泊7日 |
| 派遣人数 | 97名(団長、団員91名、日中友好会館事務局等5名) |
| 実施団体 | (公財)日中友好会館 |
| 受入機関 | 中国日本友好協会 |
| 内 容 | ・中日青年友好交流大会参加 |
| ・大学訪問・同世代交流 | |
| ・中国の経済・社会・文化・歴史等に関する視察・参観 |
主な日程
| 5月24日(土) | PM | 上海浦東空港到着 |
| 5月25日(日) | AM | 上海博物館東館参観 |
| PM | 上海人民対外友好協会、駐上海日本国総領事館との昼食会、南昌市へ移動 | |
| 5月26日(月) | AM | 滕王閣参観 |
| PM | 南昌大学訪問・交流、南昌VR産業基地参観、歓迎会 | |
| 5月27日(火) | AM | 景徳鎮市へ移動 |
| PM | 国際陶磁博覧交易センター参観・絵付け体験、農村振興視察、陶渓川文化エリア参観・陶磁工業遺産博物館参観 | |
| 5月28日(水) | AM | 陶陽里歴史文化街視察 |
| PM | 北京市へ移動、永定門参観 | |
| 5月29日(木) | AM | 北京師範大学訪問・交流 |
| PM | 中日青年友好交流大会、歓送会 | |
| 5月30日(金) | AM | 故宮博物院参観 |
| PM | 帰国 |
参加者の感想
◆訪中前、私が抱いていた中国のイメージは、日本のメディアやSNSから得た情報に大きく影響されていました。それらの情報は、時として一面的であり、知らず知らずのうちに私のなかに中国に対するネガティブな感情や先入観を植え付けていたように思います。しかし、実際に中国を訪れ、現地の人々の文化や生活に触れる中で、その先入観は大きく揺らぎました。私がこれまで「日本人」というフィルターを通して中国を評価し、理解したつもりになっていたことに気づかされました。交流した学生や市民の方々は皆温かく、私たちを一個人として歓迎してくれました。
今回の経験を通じ、今後の日中関係をより良いものにしていくためには、私たち一人ひとりの意識が重要だと強く感じました。「日本人」「中国人」といった民族意識や国民性という大きな枠組みで相手を見るのではなく、目の前にいる一人の「個人」として向き合い、理解しようと努めること。その積み重ねこそが、真の友好関係の礎となると感じました。
◆今回の訪中を通じて、私が最も強く感じたのは、中国における国家としての自己イメージの発信力と、それを支える若者の強い愛国心でした。視察先では、建造物や観光施設の規模、都市インフラの整備状況から、中国の急速な経済発展と国家戦略の成果を目の当たりにしました。同時に、それらがいかに計画的に「国の魅力」として演出されているかにも注目させられ、プロモーションにおける戦略性の高さを実感しました。
また、現地の学生との対話を通じて、SNS等で得ていた中国像とは異なる、より多面的で現実的な姿を知ることができました。彼らは自国に対する強い誇りを持ちつつ、私たち日本の若者にも真摯に関心を寄せており、相互理解の可能性を感じさせてくれました。本交流を通じて得た最大の収穫は、「先入観の打破」と「実際に現地を見ることの意義」です。今後は一層、国際社会を見る目を養い、多角的な視点から物事を捉える姿勢を大切にしていきたいと考えています。
◆南昌大学での交流では、日本語を学んでいる大学1年生の方から日本語の教科書を見せてもらいました。最初のページから、日本語特有のあいまいな表現を含む会話文が掲載されており、中国における学習姿勢の高さに驚かされました。中国は人口が多く、大学に入る競争は日本とは比べものにならないほど厳しいのではないかとも感じました。また、日本のアニメが好きな学生が多いという印象も受けました。1日目の夜、散歩をしていたところ、思ったより遠くまで行ってしまい、帰りはタクシーを利用したいと考えて、近くのコンビニにいたおじさんに相談しました。すると、快くタクシーを手配してくださり、なんとタクシー代まで支払ってくださいました。インターネットなどで見かける「人のつながりや温かさがない国」という印象とはまったく異なり、実際には心の通った優しい人たちがいると実感しました。もちろん、自分が良い面ばかりを見ている可能性もありますが、それでもなお、現地の「本当の姿」をもっと多くの人に伝えるべきだと強く感じました。
北京師範大学では、学生の方にキャンパスを案内してもらいました。ラフで日常的な会話が多く、生活も自分とそれほど変わらない、普通の大学生だと感じました。「国」という壁は意外と低いのかもしれないと、思わされました。
◆もともと中国に関心はあったものの、実際に足を運んで見た「生の中国」は、非常に興味深いものであった。アジア、さらには世界の超大国とも言える中国。そしてその原動力である14億人の人口の活気を目の当たりにすると、彼らがどのように思考し、どのように生きているのかを知りたくなった。そこで今回の訪中を機に、中国の政治および人民の根底にある思想への理解をさらに深めたいと考えるようになった。中国の至る場所で、「社会主義核心価値観」と大きく書かれた看板「政治宣伝・プロパガンダ」を目にした。その下には、「富強」「民主」「文明」「和諧」「自由」「平等」「公正」「法治」「愛国」「敬業」「誠信」「友善」という12の語句が並んでいた。私はこの中でも特に「公正」と「法治」に関心を持った。以前、習近平国家主席の愛読書の一つが『韓非子』であると聞き、岩波文庫の『韓非子(第1冊)』を読んだことがある。もちろん、韓非が生きた時代と現代中国は大きく異なる。だが、それでも現代中国の掲げる「公正」「法治」には、韓非子の思想と通じるものがあるのではないかと感じた。 我々日本人は、戦後、西洋的な民主主義思想を取り入れ、「民主」=「法の支配」と考えるようになった。その結果、社会は安定的に機能し、アジアで最初の民主主義経済大国となり、西側諸国の一員としての地位を築いてきた。比較として、西側の「民主」と中国の「民主」の関係を、「法の支配」と「法治主義」の対比として捉えてみると興味深い。どちらに優越があるのかを議論することは、それぞれの社会に暮らす人々の思想に深く関わるため、一概に判断することはできない。ただ、双方の価値観は相互に尊重されるべきだと私は考える。今回が初めての訪中であったが、私が想像していた中国とは全く異なる姿がそこにはあった。一つだけ、想像と変わらなかったのは中国の人々に対する印象である。これまで日本で関わった中国の人々は皆親切であり、その印象は今回の訪中で確信に変わった。
一方で、大きく異なっていたのは都市と経済の発展ぶりである。私の乏しい予測とは異なり、どの都市も非常によく整備されていて、洗練された都市計画を垣間見ることができた。また、農村地域であっても道路や公共施設は美しく整備され、地域内で経済がしっかりと循環している様子がうかがえた。 今回の訪中を通じて、私の中国に対する見方は大きく変わった。人生100年時代と呼ばれる今、中国と関わっていくためには、その根底にある思想を理解し、尊重することが何より重要であると感じた。