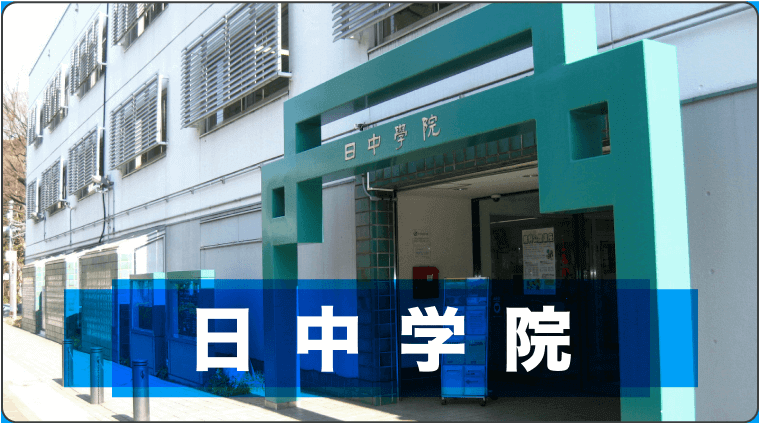2025年度「日本青年友好植樹団モンゴル派遣」
2022年11月の日本・モンゴル首脳会談での共同声明に含まれている、日本によるモンゴルの「10億本の植樹」国民運動推進に向けた協力の一環として、環境分野を研究する、または同分野に関心を持つ大学生・大学院生をモンゴルに派遣しました。
植樹活動、環境保護に関するプログラムや、モンゴルの青少年に対する環境にかかる啓発活動等を通じて、環境分野における日本・モンゴル間の相互理解ならびに対日理解の一層の促進を図ることを目的として実施しました。






Contents
Highlight
モンゴルの環境分野における研究・取り組みを理解
モンゴル科学アカデミー地理学・地生態学研究所では、モンゴルの土壌や永久凍土、物理・地理学等、同研究所で行われている研究についての説明を受け、自然環境・気候変動省では、2026年にモンゴルで開催される気候変動枠組条約第17回締約国会議の概要や「10億本の植樹」の取り組み等について説明を受けました。
ホスタイ国立公園では、公園内で行われている草原保全と野生動物保護の現場を視察しました。草原の劣化のメカニズムや土壌回復の課題、保全対象動物と環境の繋がり等、さまざまなことを学ぶことができました。
モンゴルの青少年との交流および啓発活動
モンゴル国立大学付属バイガル・エへ高校および第149番学校で、エコクラブの活動の紹介を受け、モンゴルの環境教育について理解を深めました。また、第149番学校では、エコクラブの生徒とともに植樹活動を行いました。
日本モンゴル学生フォーラムにおいては、両国の学生が環境保護に関する研究発表および意見交換を行い、互いの研究内容や現状に対する理解を深めました。その後の交流会では、和やかな雰囲気のもと、親睦を深めることができました。
実施概要
| 派遣期間 | 2025年9月28日(日)~10月4日(土) 6泊7日 |
| 派遣人数 | 13名(団長、団員9名、事務局3名) |
| 委託機関 | 外務省 |
| 受託機関 | (公財)日中友好会館 |
| 受入協力 | 在モンゴル日本国大使館 |
| 内 容 | ・植樹活動 |
| ・環境保護に関するプログラム(視察、ワークショップ・意見交換、関係者との交流等) | |
| ・モンゴルの青少年に対する環境にかかる啓発活動(学校訪問・交流等) |
主な日程
| 9月28日(日) | PM | モンゴル ウランバートル到着 |
| 9月29日(月) | AM | 在モンゴル日本国大使館訪問、モンゴル科学アカデミー地理学・地生態研究所訪問 |
| PM | モンゴル国立大学附属バイガルエヘ高校訪問・交流 | |
| 9月30日(火) | AM | 自然環境・気候変動省セミナー |
| PM | 日本モンゴル学生フォーラム、モンゴル青年との交流会 | |
| 10月1日(水) | AM | 日本人死亡者慰霊碑訪問、ノゴーン・ノール公園(資料館「さくら」)視察 |
| PM | ホスタイへ移動、ホスタイ国立公園視察 | |
| 10月2日(木) | AM・PM | ホスタイ国立公園視察 |
| 10月3日(金) | AM | ウランバートルへ移動 |
| PM | 第149番学校訪問・植樹活動 | |
| 10月4日(土) | AM | 帰国 |
参加者の感想
◆モンゴルの遊牧民の生活が自然環境や社会の変化を強く受けていることが分かりました。経済体制の転換や地球規模での気候変動など、彼らの生活に大きなインパクトを与える出来事のあおりを受けて、過放牧による砂漠化が起こったり、寒害により経済的に不安定となった遊牧民がウランバートルへ移り住むことなどによって都市の過密化が起こったりするなど、一見個別に見えるような様々な分野の問題が実際は一つに繋がっているということを、今回の一連のプログラムを通してよく理解できました。ひいてはこれは単にモンゴルという一つの国だけの問題ではなく、各国が連携し解決に向けて努力する必要がある問題であることも強く感じました。
◆一つ印象に残っているエピソードとして、バイガルエヘ高校に訪問した時の高校生への質問で「みなさんは遊牧民になれると思いますか?」と聞かれた際に、数人の生徒が照れくささ混じりの表情で誇らしげに手を上げていたのがとても心に残っています。都市での生活に慣れている人々が実際に遊牧民として適応できるかはまた別の問題として、それでも彼らが遊牧民というモンゴルのアイデンティティに対してとても誇りを持っているんだろうなと感じられたのがすごく良かったです。“遊牧民”は単なる一次産業とはまた異なると思いますが、日本では一次産業へ従事する人々の高齢化やなり手不足の問題が深刻化している一方で、“遊牧”が大切な伝統や文化と非常に強く結びついているモンゴルでは、そういった分野が今もこれからも魅力的なものの一つとして捉えられていくのかなという風に感じました。
◆現在のモンゴルの形は、単純な気候や文化だけでなく、歴史的な背景にも大きく影響されており、食生活や生活習慣、街の色や人間性まで全てが日本と一部似ているようで、大きく異なる新鮮なものでありました。また、現在の目覚ましい発展が見られるからこそ生じるような環境問題も多く、今後の成長を見据えるうえで、これからの対策を慎重に練っていく必要があると思いました。
また、年齢の近しい現地の人との直接的な交流により、同じ基準で価値観比較ができ、文化的理解が深まりました。
◆第一に印象に残った点はモンゴルの食文化についてです。遊牧民は基本的に夏場は白食(乳製品)を食べて過ごし、冬場は赤食(肉料理)を食べて過ごすというガイドさんの解説が印象に残っています。水が少ないためミルクやヨーグルトなどの乳製品で水分を補給したり、冬場はカロリーの違うヤギ肉、馬肉、羊肉を使い分けたりするのだと、遊牧民の知恵を学ぶことができました。
第二に印象に残った点はモンゴルの生態系についてです。ホスタイ国立公園に行った際、直接植物や動物を見る機会をいただきました。乾燥・寒冷という厳しい環境条件から草本植物が優占している中、シラカンバが唯一の木本植物として生育しているのが興味深かったです。公園内にはタヒと呼ばれるウマの仲間が500頭ほど生息しており、その頭数にも関わらず「オスを見ればそれぞれどの群れか分かる」という先生の話に驚きました。また、ウランバートル市内には街路樹としてポプラやマツが植えられており、日本との気候の違いを感じられました。
第三に印象に残ったのは学校教育についてです。第149番高校に伺った際、身体的・知的障害のある子供たちも快適に勉学が行えるようバリアフリーな環境が設けられていました。特に「どの年に障害を持った子供が入学してくるか分からない。そのため全教師が配慮を行えるように勉強している」という校長先生の話が印象的で記憶に残っています。また、ちょうど訪問日は「先生の日」と呼ばれる生徒が先生に授業を行って日頃の感謝を伝える日だと知り、日本にもこういったイベントがあったら面白いかもと思いました。
以上の三点が特に印象に残っているモンゴルでの記憶です。食文化、生態系、学校教育のどれをとっても日本とは異なる点がありました。しかし決してそこに優劣はなく、環境の違いが生活の工夫に変化を及ぼしているだけなのだと感じました。こういったモンゴルの文化、環境、教育について日本でも少しずつ伝えていきたいと考えました。