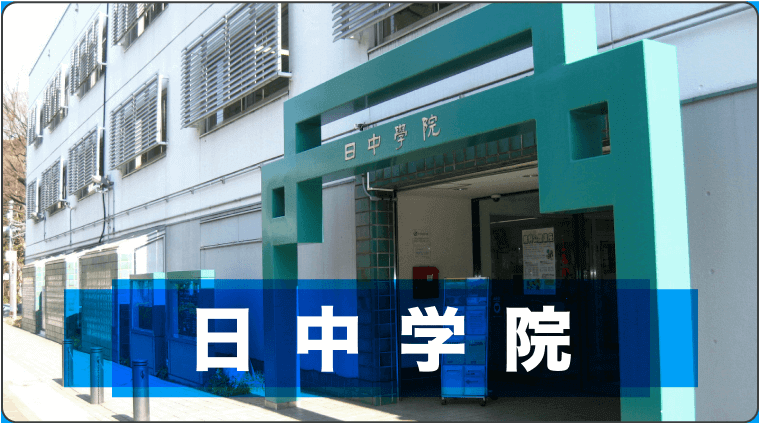「JENESYS2025」日本青年研究者訪中団
本事業は、日中友好会館と中国社会科学院との協力により実施するもので、日本の青年研究者を中国に派遣し、中国社会科学院をはじめとする中国の研究機関・政府関係部門等を訪問し、青年研究者及び関係者との交流を行い、日中両国青年間の友好を深めたほか、訪中テーマ「デジタル時代の伝統文化」に関する視察や地方都市の視察・参観等を通じて、中国についての多面的な理解を深めました。






Contents
Highlight
外交部、共産党中央対外連絡部の政府・党関係者と交流
外交部ではアジア司 聶佳参事官らと懇談。聶佳参事官より、日中関係や伝統文化を含む中国の現状が紹介され、団員からは自己紹介と中国への質問を出し、その質問に応じる形で率直な意見交換が行われました。共産党中央対外連絡部では、同局の若手職員らが出席し、「互いの国への印象」「日中関係」「自国の現在の姿」をテーマに、日中代表者3名ずつによる発表が行われました。
日中青年研究者による座談会・中国研究者による講義に参加
中国社会科学院日本研究所の学者との自由討論形式での座談会を皮切りに、山西省大同市では大同市宣伝部・文物局の幹部や雲崗研究院・大同大学の学者らが参加する「雲崗芸術のデジタル化」「伝統文化・文物の保護と社会発展」等をテーマとする座談会に参加したほか、中国歴史研究院では考古研究所の研究員による「崑崙石刻」に関する講義を受けました。いずれも日中の研究者が率直な意見交換を行い、双方にとって大変学びの多い交流となりました。また、大同市での座談会を受けて、団員より日本で「雲崗石窟」に関する展示会を行いたいとの提案もあり、日中文化交流の継続という点でも大変意義深い訪問となりました。
訪中テーマに関する視察や北京・地方都市の視察を通じ中国を多面的に理解
訪中テーマに関して、デジタル技術を使い、RPGゲーム「黒神話・悟空」の背景となった懸空寺・雲崗石窟を視察したほか、大同市博物館と中国考古博物館の視察では、中国伝統文化の神髄に触れただけでなく、3Dデータが組み込まれた展示ガラスタッチパネルディスプレイを見学者の誰もがそれを操作できるという最先端のデジタル技術に触れることもできました。
実施概要
| 派遣期間 | 2025年10月19日(日)~10月25日(土) 6泊7日 |
| 派遣人数 | 10名(団長、団員7名、日中友好会館事務局等2名) |
| 実施団体 | (公財)日中友好会館 |
| 受入機関 | 中国社会科学院 |
| 内 容 | ・中国社会科学院訪問及び中国青年研究者との意見交換 |
| ・中央および地方政府機関訪問、研究機関訪問・交流 | |
| ・その他、交流テーマ「デジタル時代の伝統文化」に沿った活動、中国の経済・社会・文化・歴史等に触れるプログラム等 |
主な日程
| 10月19日(日) | PM | 北京着 |
| 10月20日(月) | AM | 中華人民共和国外交部 訪問 |
| PM | 「可能有書」書店・27院児 視察、前門大柵欄 参観、中国社会科学院日本研究所主催歓迎会 | |
| 10月21日(火) | AM | 日中青年学者座談会(中国社会科学院日本研究所の学者との交流) |
| PM | 中国共産党中央対外連絡部 訪問、在中国日本国大使館との夕食会 | |
| 10月22日(水) | AM | 山西省大同市へ移動(高速鉄道) |
| PM | 懸空寺 視察、大同市主催夕食会 | |
| 10月23日(木) | AM | 雲崗石窟 視察 |
| PM | 大同市博物館 視察、大同市博物館にて座談会、大同古城 参観 | |
| 10月24日(金) | AM | 北京市へ移動(高速鉄道) |
| PM | 中国考古博物館 視察、中国歴史研究院の学者との交流、歓送報告会 | |
| 10月25日(土) | AM | 帰国 |
参加者の感想
◆中国では、中国社会がすでにかなりの発展をみせているにもかかわらず、日本人が中国に良いイメージが無いのは、メディア等の影響で中国の真の姿を見ていないからとの認識が根強い。それ故に、中国は日本人を中国に招いて等身大の中国を見て欲しいと考えている。こうした話が訪問中幾度も繰り返されていたことが印象的であった。また中国でも来るべき高齢化社会に備え、高齢者が活躍できる地域コミュニティの形成といった取り組みが行われるようになっている。ここでは、共通の課題に長らく直面している、日本に学ぼうとする姿勢が強かった。こうした社会問題の解決に関しては、より一層お互いに知恵を出し合う余地がありそうに思う。そして大同市博物館や歴史研究院での座談会では、中国による最新の文物保護の取り組みや、考古発掘の成果を紹介していただけたが、その中でも日本人の過去の業績がかなり認知されており、重視されていることがうかがえた。やはり伝統的な面に関して、もっとも深く理解しあえるのが日本と中国だと思う。
◆私は、中国の伝統文化に親しみを持っていたつもりでした。しかし、恥ずかしながら、実際は日本の源流という意味で中国の文化を見ていたに過ぎず、中国自身の文化、そして現代の中国について関心を向けていたかと問われれば、そうではなかったということに気づきました。これは中国の方と対話したことで気づいたことでした。一度、日本というフィルターを通さずに中国について目を向けてみれば、長い歴史と地方ごとに特色のある景色や文化の違い、一括りにはできない多様性に満ちた国であることに気づきます。
また、今回の訪中で、現在の中国では、博物館や美術館、遺跡などに若い人が多く来場されていることを知りました。文化への関心を高めるためにどのような取り組みが重要であるか興味があったので、現在の中国の姿から学ぶことは多いと感じました。そのなかでも特に、伝統文化の現代化という言葉が印象に残っており、博物館だけでなく街の中や日常に、文化が浸透している様子を実際に見ることができました。
都市化、電気自動車の普及、電子決済の普及など、先端的な街の様子に、これまでのイメージとは異なる中国の姿を見ることができました。
◆どの訪問先でも、伝統を保存しつつ、積極的に活用していこうという姿勢が見られた。考古学博物館では、展示ケース自体に文物の見どころが浮かび上がってくるという最新技術が用いられており、今後の博物館のあり方を大いに考えさせられた。雲崗石窟では、歴史学的な観点から造像銘を読む際に問題となる鮮卑の習俗と柔然と北魏の関係について疑問を述べ、その知見についてご教示を得ることができた。また最新技術でこれまで判読が難しかった墨書を読むことができるようになりつつある状況についても伺えた。中国歴史研究院考古学研究所での交流では、青海省の発掘担当者に古代交通路の発掘の意義を問い、蘭州から青海省へ至るルートと四川から青海省に至るルートのどちらも重要ルートであることを確認できた。専門的な交流は同じ知的基盤に立って行うもので、相互理解促進に不可欠な行為であると改めて感じた。