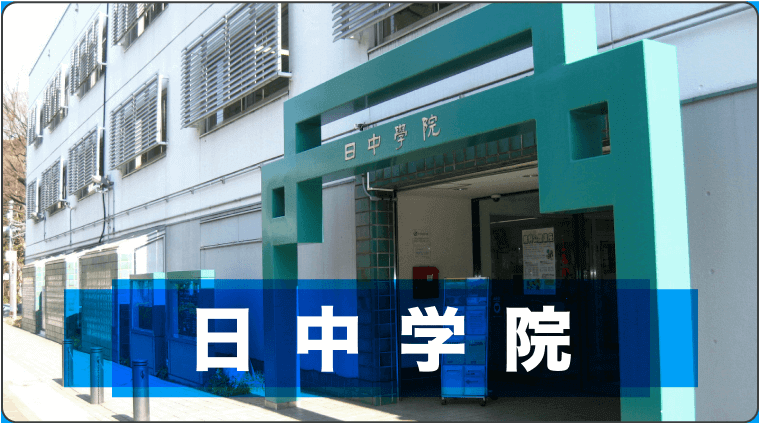今どき北京はこう歩く・2025年度版
第3回
第3回
新暴走族は
「待業青年」が多いらしい
新・暴走族?登場
ありがたいことに「北京の弟」は、私が行きたいところはすべて連れていってくれる。滞在中「今日は何が食べたい?」が挨拶がわりだ。いい「弟」を持った。
さて、数あるレストランのうち、絶対にはずせないのが「那家小館」である。
清朝時代の宮廷料理を基礎としているが、気取ったものではなく、気軽に味わえる満州料理である。二十年ほど通い続け、なかでも海老を甘辛く揚げた「酥皮大明蝦」と西太后が好んだ菓子類は、コロナで北京に行けなかった間には、夢にまで見たものだ。

気取らず楽しめる、那家小館の満州料理
撮影:青樹明子

夢にまで見た、酥皮大明蝦と “西太后のおやつ”
撮影:青樹明子
このお店、以前は永安里という地下鉄駅の近くにあったが、近年、西の方に移ってしまった。 市の中心からはタクシーを使えば、十分足らずだが、渋滞すると一時間はかかることもある。
その日も道路は混んでいた。弟Kくんは、「こりゃダメだ。自転車で行こう」。
え…?北京で自転車に乗るのは二十年ぶりくらいなのに…。
「大丈夫、僕の後ろから、ゆっくり走ればいいから」
留学時代は幹線道路を激走していた私だが、すでに年を取った。感覚も鈍っている。大丈夫かなぁ…、と緊張したが、おや不思議、本当に大丈夫だった。 むしろ日本より安全なくらいだ。生まれたときから自転車に乗っているような人たちで、“下手っぴー” の避け方、何より自分の命の守り方、(一応)他人の命の守り方を熟知しているから、日本ほど怖くない。 (車天国の今は減っているけど)自転車専用道路も広々としていて快適だ。
ところが例外もある。 比較的ゆったりした動きの自転車群の隙間を縫って、新たな自転車暴走族が出現している。宅配便やフードデリバリーなどの配達専門自転車だ。
これが速い。しかも上手い。 自転車一台がぎりぎり通れるくらいの隙間があれば、そこを狙って風のごとく通過する。まるで忍者だ。

乗ってみたら、安全・快適でした
提供:青樹明子
弟Kくんの解説によると、「あれだけは仕方ないよ。みんな必死だからね。一回の配達で彼らが得る報酬は3元(約63円)、それも20分遅れるとゼロになるんだから」。
絶対に遅れず届けなきゃならない。死活問題だ。
彼らの大半は、言うところの「バイト」である。地方から出てきて、都会で職探しをしている人、経済不況で失職した人、また 何より就職が決まらず面接を繰り返している卒業間近の大学生たちである。
新暴走族は「待業青年」が多いらしい
公の数字にはなかなか表れないが、大学生の就職難はかなり深刻だ。
知り合いの大学教授によると、「トップレベルの大学でも、 就職が内定していない学生、 待業青年が非常に多い」のだそうだ。 自分の希望する職場が見つかるまで、 彼らはデリバリーなどのアルバイトをして生活をしのいでいるという。 新暴走族の何人かは、 こういう若者たちなのだろう。
「好条件の就職先を探して、ただいま潜伏中」というエリートたち。彼らはいったい、どういう職場を目指しているのだろうか。
第一は公務員なのだそうだ。特に国家公務員は 「鉄飯椀」 と呼ばれていて、食いはぐれることのない職業、日本的に言えば 「親方日の丸」 である。もともと志願者は多かったが、景気の悪化に伴って、さらに激化していると聞く。 25年採用の試験は、資格審査だけでも競争率は86倍だったという。
そしてやはり人気なのは、IT企業である。
目だけが光り・・・
今回も登場、北京稲門会の重鎮・元CCTVの章弘さん。
今や世界中で大人気のTikTokだが、その成功例から、中国では、第二のTikTokと言うべきメディアがいくつか生まれている。
そのなかで、TikTokを時には凌ぐほどの勢いを見せる新興アプリ制作会社がある。
コロナ前、章弘さんは、そのアプリ制作会社を見学に訪れたそうだ。真夏のある一日だった。
「まず驚くのは、社員たちの服装です。暑い日でね。みんなTシャツに短パン、ゴム草履という格好で出勤してくる」
日本のクールビズもメではない。
オフィスでの仕事風景にも驚いた。
社員たちの主な仕事は、送られてくる投稿動画のチェックである。国の法律に触れるような内容ではないか、社会を害するような映像ではないか、など基本的なことを確認している。
「社員たちは一日中、動画を見なければならない。ミスを犯すと会社の存続にもかかわるから、みんな真剣です。
午前中はまだしも、午後から夕方になると、みんな疲れてきて、普通のオフィスなら、だらしないと思われるような姿勢で椅子に座っている。机に足を投げ出したりしてね。疲れ切ったという表情でパソコンを見る。いつ倒れてもおかしくないような様子なのに、映像を見る目だけはランラン光っている。 驚くような光景でしたね」
オフィスには、お茶やコーヒー、サンドイッチやケーキ、果物などの軽食が常備されている。何よりも食事の時間を重要視していた中国人が、食べる時間、寝る時間を惜しんで、仕事をしているのである。世界のTikTokは、こうした仕事環境のなかから生まれたんだなぁ…。
突然会議が・・・
こんな苛酷な状況は、ITだけではない。 中国の都市部では、私営企業を中心に浸透し始めている。 私の友人は、IT企業ではないが、あまりの忙しさに簡単に会うことすらできない。
「土日も含めて、毎日残業なんです。夜8時過ぎなら、ちょっと食事してきますと言って、30分ほど抜けることができるかな?」
残業は中国の場合ほとんどがサービス残業である。
中国の友人たちと食事をしていると、携帯が頻繁に鳴り響く。 なかには、突然チャットを始める人もいて、食事中に友達とチャットか…、と驚くが、遊びのチャットではなく、緊急に仕事の会議が始まってしまったとのことだ。
中国大手企業・日本支社に勤める日本人に聞くと、日本と中国とのビジネスギャップを挙げるなら、まずは中国人の働きぶりだと言う。「996」(朝9時から夜9時まで、週6日勤務)は嘘ではなかった。
「一番の衝撃はこれでした。中国人の若いエリートたちは、こんなに働くのかという。夜中の2時3時に、仕事のメッセージが飛んでくる。 中国本社のオフィスにはハンモックが吊るしてあって、束の間の休息はそこで取るんです」
別名「ハンモック企業」。
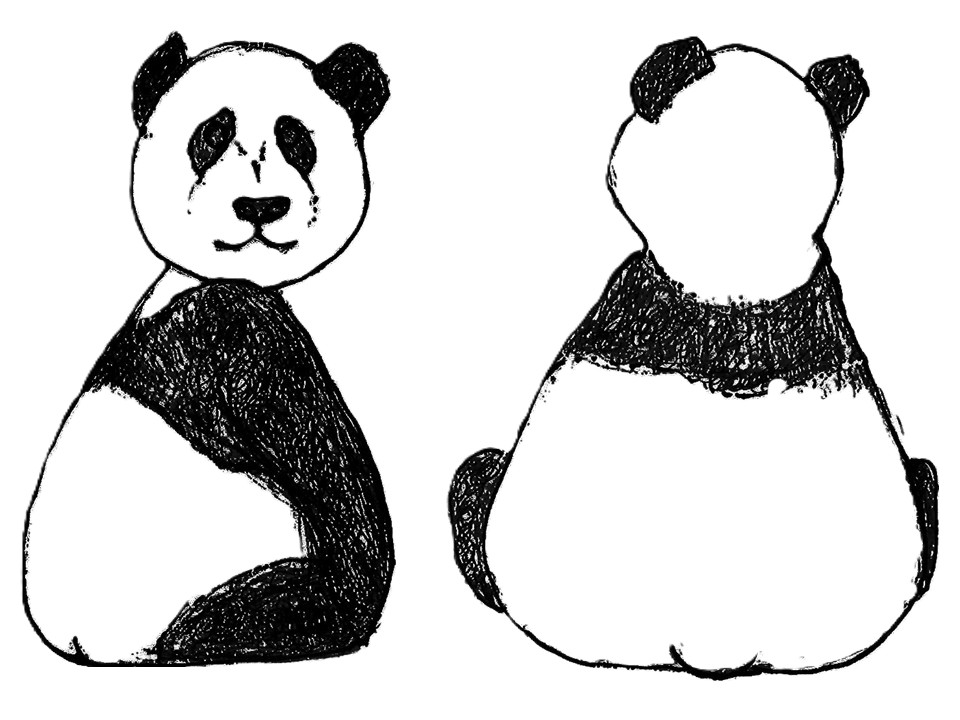
ゆっくりいこうよ!
仕事環境は、もちろんプライベートにも影響する。
中国では独身者の数が膨れ上がっていて、 今とんでもないことになっている。2018年の統計によると、 中国の独身人口は2.4億人なのだそうだ。(中国統計年鑑より)
前述の日本人が中国の本社で働く中国人の同僚に、気軽に尋ねたことがある。
「30代だよね。恋人作らないの?」
その答えが怖い。
「そんなことしている時間が全然ない」
24時間闘えますか?というのは、日本でバブル時代に流行ったCMだが、中国の働き方を見ていると、こんな言葉が浮かんでくる。
いつか来た道、戻りたくない道。
寝そべって暮らすぞ!
中国の大学入試が苛酷なことは、すでにみんな知っている。でも、何がどう苛酷なのか、あまり知らない。
経験者によると、「朝6時前に起きて、 まず自習。 朝ごはんの後学校に行って授業を受ける。 放課後も学校に残って補習や自習。 帰宅して夜ご飯。 その後深夜まで自習」…。この経験者、高三になってからは、昼間太陽を見ることはなかったと言う。
こんな思いをして大学に入るのは、憧れの職業に就きたいためだ。天文学的数字を勝ち抜いて超難関大学に入学しても、望むような仕事が得られなかったら、あの勉強漬けの日々は何だったのだろうと頭を抱えてしまうのも無理はない。
しかし、時代は変化する。
苛酷な競争を放棄し、寝そべって暮らすという「躺平」族の出現は世間を驚かせた。最近では、新たに「45度青年」「九十度青年」という言葉も出回っていると言う。
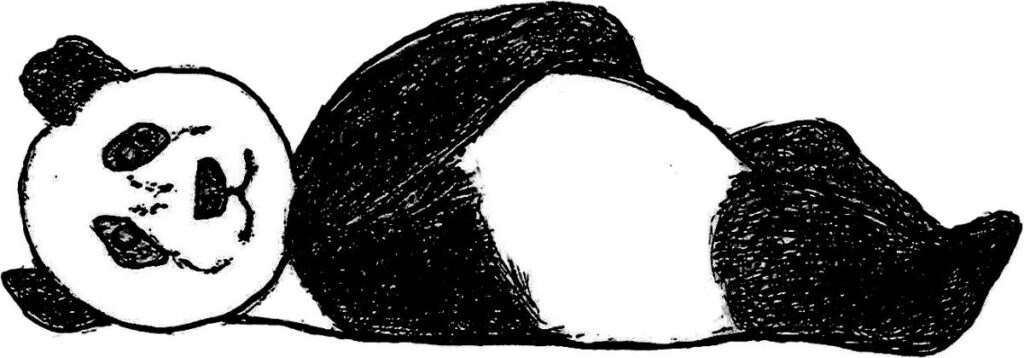
躺平 寝そべり族
「45度青年」 というのは、 生活していくうえで、 競争に巻き込まれることを避け、 しかしすべてを放棄して完全に寝そべるのではなく、 45度の姿勢を保ちながら生きていくという処世術だ。
つまり 激しい競争からは脱落したけれど、寝そべる生活にはついていけない、ならばその中間を探ろうと、微妙なバランスの上で生きる若者たちである。
「九十度青年」 は、処世術というよりも、若者たちが抱く不安な心理を表わしている。
大勢が集まる場、授業も含め食事会などで、角となる隅の場所に座ることを好み、そこ以外では不安を感じる若者たちのことを指すのだそうだ。グループに参加することを怖がり、社交に消極的で、九十度の隅に隠れるようにして生活する若者たちである。(日本の電車も、隅の席から埋まっていくが、角だと落ち着くのは日本も同じか。)
隅に隠れれば安全が確保できると考えているようだ。

45度の生き方
彼らはすべてが正規の道を逸れた 「落ちこぼれ」 のように思われるかもしれないが、 それは違う。 イレギュラーの道から生まれるスターもいる。それが「餃子さん」だ。
餃子さんとは何か。
うーん、分量が多くなってしまいそうなので、餃子さんの華麗なるリベンジ人生は、次回以降ということに。
(続く)

青樹 明子
愛知県生まれ。ノンフィクション作家。
早稲田大学第一文学部卒、同大学院アジア太平洋研究科修了。
1995年より2年間北京師範大学、北京語言文化大学へ留学し、98年より北京や広州のラジオ局にて、日本語番組の制作プロデューサーやMCを務める。2014年に帰国。著書に『中国人の頭の中』『中国人が上司になる日』『日中ビジネス摩擦』『「小皇帝」世代の中国』『家計簿からみる中国 今ほんとうの姿』等。